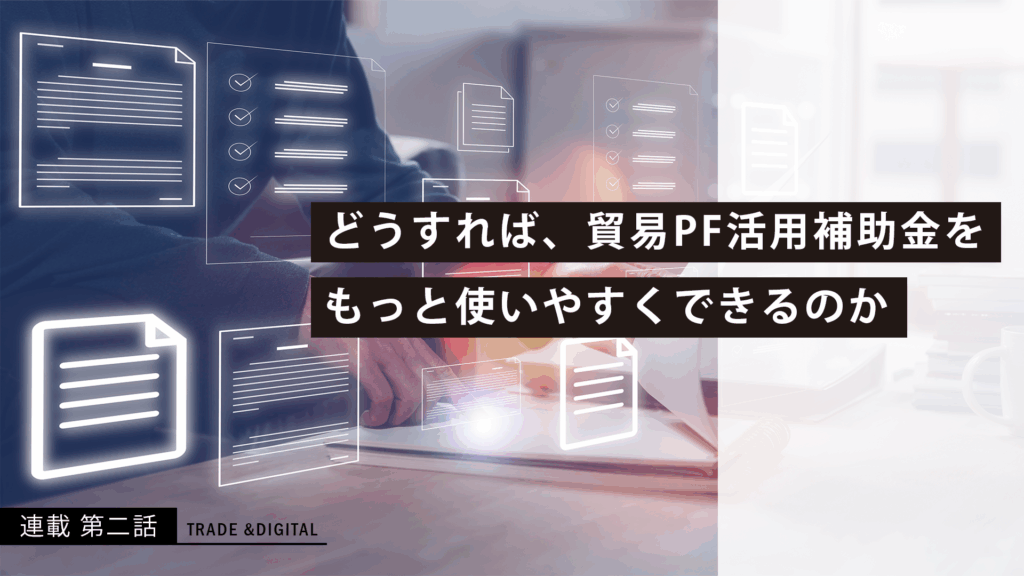birdviewは、tradigi.jp編集部がお届けする貿易+デジタルをテーマにしたコラムです。前回(ウォーミングアップ)の最後で、経済産業省が策定した「貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン」について触れました。今回は、このプランに明記されている「貿易PFの導⼊⽀援・促進」について、その具体策である「貿易プラットフォーム活用補助金」の事務局を2年間務めた経験から、補助金制度の改善提案まで踏み込みつつ深掘りします。
経済産業省が貿易DXページを開設
本題に入る前に、「貿易DX(貿易手続デジタル化)」というページが経済産業省ウェブサイトにおいて2024年3月31日に公開されたことを紹介します。奇しくもtradigi.jpの開設とほぼ同じタイミングであり、貿易+デジタルの機運を盛り上げたいという思いは官も民も共通であることを強く感じました(早速tradigi.jpからも経済産業省にコンタクトし、関連ページへリンクいただいています)。今後は、このページを起点として経済産業省が取り組む貿易+デジタルに関する情報が集約されていくものと思われます。随時チェックしておきましょう。
貿易PFは使われてナンボ
ここからが本題です。「貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン」の「工程表」において、貿易PFというキーワードは全10項目のうち「5. 貿易PFの導⼊⽀援・促進」「6. 貿易PF活⽤によるインセンティブプランの検討」「7. 貿易PFと貿易関連⾏政システムとの接続促進」「9. 貿易PFを通じた貿易相⼿国とのデータ連携事例の創出」「10.フォワーダー事業者の貿易PF参画⽀援・促進」と5項目に用いられており、大きなウェイトを占めていることが読み取れます。
貿易PFは、2024年度の補助事業において「貿易実務に携わる事業者間で貿易関連手続きをデジタル化し、貿易データを共有・活用することによって貿易実務に関連する業務の効率化・透明性向上を目的としたデジタルソリューション。貿易文書作成を含む情報処理、輸送貨物の追跡、貿易決済などの機能の全部または一部を含むもの。」と定義していました。ここからわかるとおり、貿易PFは個者ではなく複数者による相互作用を支援する仕組みです。従って、利用事業者が増えるほどに貿易手続デジタル化の効果を高めるネットワーク効果が期待できる、要は「使われてナンボ」なモノです。その導⼊を支援する補助金制度は、アクションプランにおける最初の取組みとして理にかなったものであると言えるでしょう。
2年目の進化:貿易PF活用の門戸を広げる
補助金制度は2023年度から始まり、2023年度は18事業、2024年度は30事業に対して補助金が交付されました。初年度の事業については、tradigi.jpでも活用事例を紹介していますのでぜひご覧ください。
1年目と2年目の大きな違いは、「貿易 PFの”利用”を通じた利用貿易手続デジタル化・貿易コスト削減の効果検証事業」に対する補助金が新設されたことです。システム開発に踏み込む前の段階でPFの利用を通じて行う効果検証を支援するスキームが好感されたか、2024年度の補助金交付事業30件のうち15件、実に半数がこのタイプでした。2023年度から継続されていた「貿易PF接続のためにシステム開発を伴う事業」や「貿易プラットフォーマー同士の接続を対象とした事業」では参画が難しい事業者にも貿易PF活用の門戸を拡大したという点で、このスキームには大きな可能性があるものと考えられます。
制度設計には改善の余地あり
一方、これまで2年間の制度設計が充分なものであったかというとそうではなく、補助金を活用したいが申請に至らなかった事業者もあったと聞きます。「公募の期間が短い」「事業の実施期間そのものが短い」「事業が4月から3月の年度で区切られ、システム開発プロジェクトと整合しない」「補助金申請・交付の手続に必要な工数が大きい」といった利用者の声も聴きながら補助金制度の改善を継続していくことが重要です。
では、具体的にどのような制度改善が必要でしょうか。利用者の声に基づいて考えると、「実施期間が充分確保され、年度区切りを意識することなく、公募や交付に必要な手続きが最小限である」制度が望まれていると考えられます。
「複数年度事業」を導入することで長期事業にも対応できる
まず、公募・事業期間の短さや年度区切りによって申請しづらい点については、「複数年度事業」を導入してはどうでしょうか。例えば一般社団法人環境共創イニシアチブによる「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)補助事業」において、2024年度からこの制度が導入されているという事例があります。国の年度予算に基づいている限り年度区切りは避けられないという印象もありますが、申請者(事業者)視点から見た場合にそのデメリットを最小化できれば充分なので、この事例は大変参考になると思われます
PF事業者やITベンダーによる申請代行はいかが?
次に、補助金手続の大変さについて。事務局業務を経験した立場から見ると、実務では使わないが補助金申請のためだけに求められる書類仕事、いわゆる「お役所仕事対応タスク」が多い印象でした。申請担当者が普段行っている仕事からは大きくかけ離れた性質のタスクであり、不慣れも手伝って必要以上に工数がかかっている可能性があります。
この課題を解決する案としては、例えば、かつて実施されていたエコカー補助金制度のような仕組みを導入してみてはどうでしょう。現在はCEV(クリーンエネルギービークル)補助金に引き継がれた制度ですが、この補助金はエコカーの販売店(自動車ディーラー)が申請を代行することで、エコカー購入者は「実質的な値引きの形で補助金を受け取る」ことができました。販売店は手間のかかる申請を代行するかわりにエコカーを売りやすくなり、結果エコカーが普及したわけです。こういったWin-winの仕組みを、例えば貿易PF事業者やシステム開発を行うITベンダーによる申請代行制度として導入するのです。PF利用者による申請のハードルを下げながら、PF事業者やITベンダーに対しては貿易手続デジタル化を推進する情報システムの開発を促し、かつ利用者獲得という実利を通じてビジネス面での価値向上につなげられる可能性があります。
貿易PFは使われてナンボなわけですから、それを支える補助金は貿易PFを「使う側」と「作る側」への支援が最優先。より良い貿易PFが作られ、より多くのユーザーに使われることで、貿易手続デジタル化にもいっそう弾みがつくと考えるのですが、いかがでしょう。