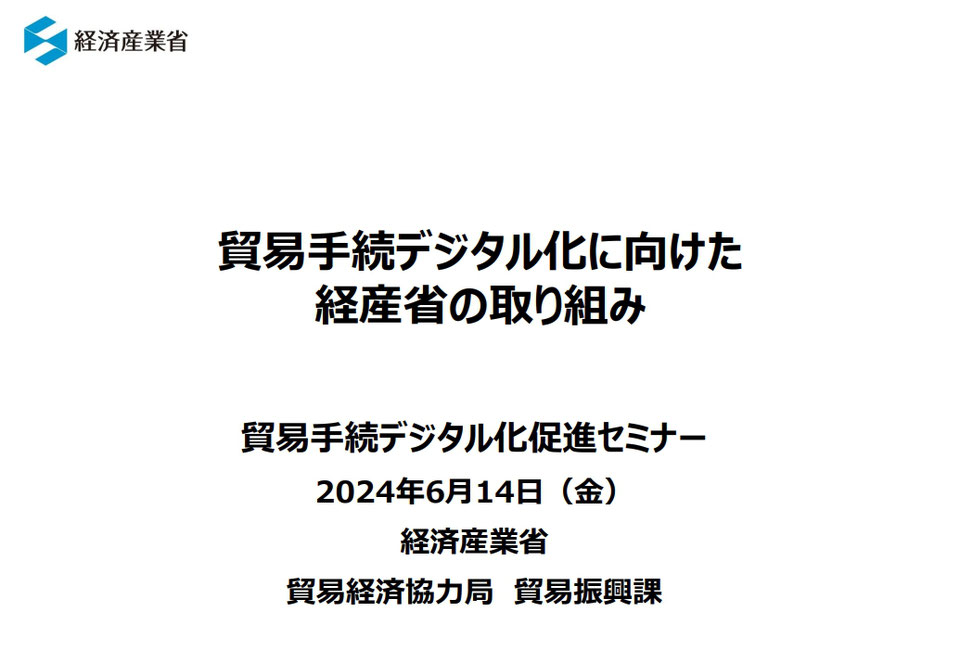ウェビナー発表資料ダウンロード:r6-webiner資料_経済産業省様
※この記事は、月刊JASTPRO 2024年8月号(第543号)の記事を再掲載したものです。
貿易手続デジタル化に向けた経産省の取り組みについて、なぜ貿易手続デジタル化を推進しているのか、何を実現していきたいのかご説明します。まず、貿易手続には紙の書類が多く、関係者も多岐にわたり、従来からアナログかつ非効率で時間がかかるというご指摘があったかと思います。これを、貿易PFを通じて貿易書類をデジタル化するとともに、デジタル化された貿易データ共有を実現していきたいと考えております
貿易PFを通じて貿易手続デジタル化を行うメリットは2つあります。まず金銭的・時間的コストです。紙を電子化するとコストが下がる。また、書類到着遅延により貨物保管の延滞にコストがかかる問題も回避できます。また、デジタル化により業務がある程度定型化され、属人化を回避でき、将来的に中堅中小企業様の新規貿易ビジネスへの参入にも寄与すると考えております。次に、有事におけるサプライチェーン耐性、昨今はパンデミックやウクライナ戦争など地政学リスクを背景に世界的に物流の混乱が生じておりますが、その際に自分の輸送している貨物が今どこにあるのかといった基本的な情報を把握することが難しく、人海戦術で関係先に聞いて回ったり、従来の輸送ルート利用が困難なときの代替輸送ルートを探すにも、これまた関係先にいろいろと聞いて回らなければいけない、そういった状況があります。これらを、貿易PFを通じて貿易取引に関わるデータを蓄積し、輸送中の貨物をリアルタイム把握するとか、洋上在庫あるいはグローバル各拠点での在庫状況も把握できるようになるとか、代替輸送ルートに関しても過去の輸送データ分析によって効率的に調査・確保可能になるとか、またサプライチェーン可視化によってチョークポイント分析、例えば特定の物資や原材料を特定の国からの輸入に過度に依存しているケースがある場合、仮にその国との貿易が絶たれてしまった場合やその輸送ルートが何らかの事情で使えなくなったなどの有事の際、代替の輸送ルートないし代替の仕入先を効率的に確保していくというような、いわゆる経済安保的な対応も、貿易PFを通じて実現したいと考えているところです。
参考として、政府の政策文書には骨太の方針と新しい資本主義の実行計画があり、いずれにも貿易手続デジタル化やサプライチェーン強靭化といった記載が盛り込まれています。政府の重点政策の一つとして、貿易手続のデジタル化が位置づけられている表れかと思います。また、例えばG20やAPECといった国際会議の場で成果文書・共同声明においても「Trade Digitalization」という言葉が盛り込まれています。貿易手続デジタル化が日本国内に限らず、世界的に重要なテーマとして現在取り上げられているという状況です。
貿易手続のデジタル化を進める上で、我々経産省としては課題が3点あると考えています。1点目が貿易PFユーザーの拡大です。貿易PFはユーザーが増えれば増えるほど利便性やメリットが増えるといういわゆるネットワーク効果を有するため、アーリーアダプターと呼ばれる層に対して導入の負担がかかります。そこで、初期導入にかかるシステム関連の経費を政府としてサポートしていきたいということです。2点目が、貿易分野におけるデータ連携の拡大です。民間企業で貿易PFサービスを提供される企業様は複数あります。例えばある企業はAという貿易PFを使い、別の企業はBという貿易PFを使っていて、AとBの間でデータ連携がスムーズに行われない場合、これはユーザーにとって非効率な状況であり、複数のプラットフォーマーと接続しなければならない等、二重三重でコストがかかることになります。3点目は貿易相手国との連携です。国内の手続を完全に電子化したとしても、肝心の輸出先国の通関時に紙で提示を求められるという事情があると、完全な貿易手続電子化・デジタル化の実現には至らないかと思います。そのためASEANをはじめとする日本にとって重要な貿易相手国との間で紙を一切使わない貿易手続デジタル化が求められているところです。
経産省では、昨年度から貿易PF活用による貿易手続デジタル化推進事業を実施しています。まず、貿易PFをお使いになる企業様が、社内のシステムと貿易PFのシステム連携を行う際の経費、あるいは初めて貿易PFを使うにあたって効果検証をされたい場合に実証的に貿易PFを利用する、そういった際にかかる経費を補助金でご支援させていただくというスキームになっております。また、貿易PFの利活用推進に向けた検討会を昨年11月から開催しております。補助金事業以外に、貿易に携わる官民の関係者が連携する形で貿易手続デジタル化、貿易DXを一緒になって進めていこう、そのモメンタム作りというところを目的として、今年の3月に中間まとめを行い、現在関係省庁との間で貿易手続デジタル化に向けたアクションプランを作成しているところでございます。
中間まとめの概要としては、荷主企業、貿易PF提供企業、経産省をはじめ関係省庁の三者で会合を行い、それぞれの立場で貿易手続デジタル化に向けて必要とされる取り組み、あるいは現在抱えている課題を議論しました。荷主企業様からは、貿易PFをまず使ってみること、また貿易DX分野に社内的に取り組むための人材育成、社内的に貿易デジタル化の重要性・認知度を高めていくといった課題が挙げられました。貿易PF提供事業者様からはプラットフォーム間の連携、金融機関・商工会議所等の貿易関連機関との連携、貿易PF企業による業界団体の立ち上げ検討等、こうした取り組みを通じたユーザー拡大を挙げられております。最後に、政府としてはアクションプランにおいて紙の貿易文書・手続をデジタル化していく、例えば電子船荷証券の法制度の整備や港湾手続のデジタル化推進、貿易PFへの接続支援、貿易PF間の連携支援などを盛り込んでいます。
貿易PF利活用推進に向けた検討会の中間報告書をホームページに掲載しておりますので、ご一読いただければと思います。セミナーご参加の皆様、状況はそれぞれ異なるかとは思いますが、この後のお話をご参考として貿易DXにチャレンジいただければと思います。政府の支援も積極的にご活用いただければと思いますし、官民一丸となって日本として貿易DXを頑張っていければと思っております。以上、ありがとうございました。