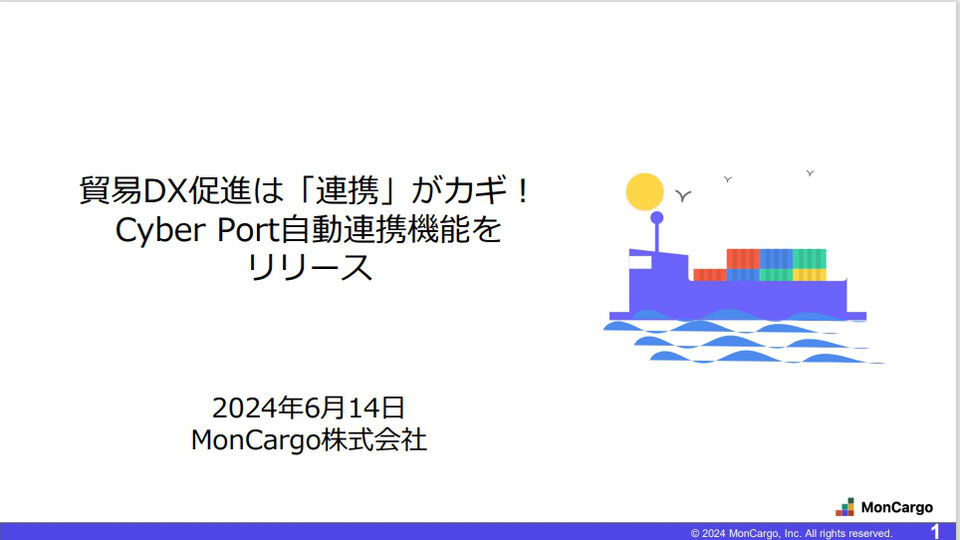ウェビナー発表資料ダウンロード:r6-webiner資料_MonCargo株式会社様
※この記事は、月刊JASTPRO 2024年8月号(第543号)の記事を再掲載したものです。
本日のテーマは「貿易DX促進は連携がカギ」とさせていただきまして、皆様の自社システムと、これから紹介させていただく「MonCargo」や「Cyber Port」との連携をどうしたらいいか、弊社の事例を聞いていただければ幸いです。
MonCargo株式会社は2022年3月に創業したベンチャー企業です。本船動静確認サービス「MonCargo」を開発しています。私の経歴を紹介させていただきますと、もともとは、プラットフォームやメーカーの立場でEC(電子商取引)を経験していまして、特に貿易・物流業界にいたわけではありませんでした。「貿易実務もやってなかったのになんでMonCargo作ったんですか?」とよく聞かれますが、きっかけはメーカーで在庫確認やフォーキャスト(在庫等の予測)をやっていたときのことです。ちょうど2021年頃のコロナ禍によるサプライチェーン大混乱の時に遅延や欠品を何度も経験し、社内で「なんで遅れるんですか?」と聞いても「オーシャン(海上輸送)なので遅れるのは当たり前です」とよく言われていました。そんなわけあるかと思っていたところ、専門商社等の方に話を聞く機会があり、確かにETA(Estimated Time of Arrival:到着見込時刻)はとても遅れること、さらにそのETAの確認にずいぶん手作業が発生していることを聞き、だったらこれを自動化するサービスを作ってみようということで開発したのがMonCargoです。
MonCargoは「本船動静を一元管理するシステム」です。例えばブッキング番号、B/L番号、コンテナ番号のいずれかを入力いただくと、複数の船会社さんのETD(Estimated Time of Departure:出発見込時刻)、ETA、船の本船名をモニタリングし、変更があったら通知するサービスです。提供価値は3つあり、1つ目が複数船会社の情報を一元管理できることです。各船会社のサイトでETAを確認する必要がなくなります。私が話を聞いた専門商社の方いわく、表計算ソフトにブッキング番号とB/L番号をずらっと書き、毎朝各船会社のサイトを確認して最新の位置やETAに変更がないかを確認するという作業をされていました。MonCargoを使うとこれらが自動で反映されるので、各船会社のサイトを都度確認する必要がなくなります。2つ目は担当者の業務負荷軽減です。遅延・変更があったらメールでプッシュ通知されます。自分から見に行く手間がなくなり、業務負荷が削減できます。最後は関係者共有の迅速化です。MonCargoにアカウントがなくてもURLを共有して船積み情報を確認でき、コミュニケーションコストが削減できます。メール通知やコンテナの追跡状況もチーム内で共有できるようになります。なお、自社システムとのデータ連携は「API連携」または「埋め込み」で可能です。
それでは次に、補助金申請の経緯と、どういった効果があったのかを説明いたします。MonCargoの開発方針は「ユーザーの悩み解決、ユーザーファースト」です。Cyber Port連携を開発するにあたっても、ユーザーのお悩みから生まれました。「MonCargoにもCyber Portにも、同じデータを何回も入力するのは大変」という声や、「Cyber Portで情報集約したいけども、Cyber Portは動静確認がまだできない」という声がありました。ではCyber PortとMonCargoをつなげれば、ユーザーとしては一気通貫で管理できるのではないか、ということで開発に踏み切りました。これが、今回補助金申請した背景です。
補助金を活用したい方でCyber Port連携したい方には特に参考になればと思いますが、まずCyber PortのAPIドキュメントはとても充実しています。先ほど国土交通省の長津様からもAPIを採用しているというお話がありましたとおり、弊社からのCyber Port連携もAPI経由です。Cyber Portのアカウントをお持ちの方は、ヘルプから「API利用ガイダンス」が見られます。開発者にはとても分かりやすいです。検証環境用のAPIドキュメントもユーザーフレンドリーで、こちらも開発者にはとてもわかりやすくなっています。次に、サポートが丁寧です。ドキュメントを見ながら開発していて、どうしてもわからない点があり問合せした際、担当者さんが大変親切でした。Cyber Portと提携されている開発ベンダーさんも丁寧にサポートくださいまして、テスト環境、検証も密にしていただき、開発を問題なく進めることができました。
補助金によって得られた効果として、1つ目は貿易実務担当者がCyber Portに船積登録した場合、MonCargoのID・パスワード設定とCyber Port連携が初期設定されていれば、重複するデータ入力にかかる時間がゼロになり、工数が圧倒的に削減できます。2つ目は、Cyber Portでデータ集約されている方が本船動静確認する際、通常は冒頭申し上げたとおり各船会社のサイトで確認しないといけませんが、MonCargoとCyber Portの連携により本船動静の確認時間が圧倒的に削減できます。3つ目は、関係者への共有もMonCargoのURL共有やメール通知を使っていただくことで約6割削減でき、これらの効果によって業務効率化につながっています。
冒頭、貿易DXは連携がカギとお話させていただきました。皆様の自社システムと貿易PFを連携・接続していただくことで貿易DXが進むと考えています。自社でゼロからシステム開発してみようと思われた方もいらっしゃると思いますが、開発にはイニシャルコストやメンテナンスコストがかかります。連携を視野に入れた開発をして、補助金を活用することで貿易DXを実現していくというのが良いのではないかと思っています。
MonCargoでは、オンラインデモや個別相談も実施しております。無料トライアルもありますので、ぜひアカウント登録いただき、本船動静確認の実際の動きや、Cyber PortとMonCargoの連携方法を確認いただいて、「自社でこれができればこういうふうにDX進むのではないか」という視点で見ていただければと思います。ぜひ積極的にトライアルいただければ嬉しく思います。なお、「モンカーゴ」で検索すると情報が出てこないので、「MonCargo(もんかるご)」で検索していただければと思います。本日はありがとうございました。