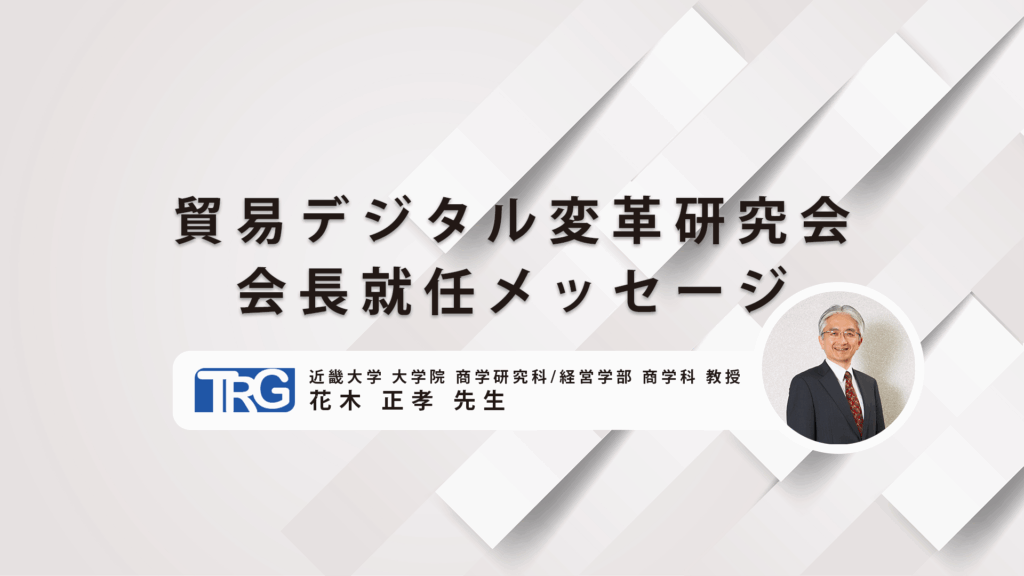この記事では、近畿大学教授 花木 正孝先生より貿易デジタル変革研究会(TRG)会長就任のご挨拶をいただきましたので紹介します。花木先生は、銀行勤務を経て研究者への道に入られ、そのキャリアを生かして貿易取引における電子化、FinTech活用、マネー・ローンダリング防止等を精力的に研究されておられます。2025年春には日本貿易学会、日本港湾経済学会においてそれぞれ学会賞 1を受賞されました。TRGのミッションやこれから取り組むべき活動について、会長からのメッセージを是非ご覧ください。
会長就任メッセージ
貿易デジタル変革研究会(Trade digital transformation Research Group:TRG)初代会長に就任した花木でございます。就任にあたり、TRG発足に至る経緯のご説明、ご挨拶と共に、TRGの果たすべき役割について述べさせて頂きます。
TRGの事務局である一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)は、1974年の設立以来、書式標準化、電子化への提言、調査・研究成果の普及・広報活動などわが国の貿易関係手続の簡素化に努めるとともに、貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business:国連CEFACT)の貿易円滑化組織(National Trade Facilitation Body:NTFB)として登録されています。
国連CEFACTのミッションは、「貿易円滑化の実現と電子ビジネスの標準化」であり、初期には、貿易書類標準化の推進(1950~80年代)やEDI(電子データ交換)などの国際標準の策定を推進(1980~90年代)しました。その後、インターネットの普及に伴い、XML(拡張マークアップ言語)を使った次世代EDI標準(ebXML)の開発と普及促進活動(2000年代以降)を行ってきました。
現在、多くの分野で、デジタル変革(Digital Transformation:DX)の必要性が指摘されております。経済産業省(2024) 2は、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義しており、これは貿易デジタル化においても例外ではありません。わが国においても貿易関係者のDXへの機運は上昇しており、この機会を捉え、国連CEFACT活動に関わる専門家に加え、より多くの関係者に門戸を拡大するなど、参加者層の拡大や活動効果の最大化を実現するため、TRGを発足させました。
ここで、TRGの果たすべき役割について述べさせて頂きます。Chesbrough(2003) 3は、IT技術の発展やグローバル化の進展に伴い、オープンイノベーション(Open Innovation:OI)が重要になってきたと指摘しています。OIは「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである。」と定義され、DXを進める上でも重要であると考えられます。TRG(及び事務局であるJASTPRO)が掲げる「TRG/tradigi.jpの運営を通じて貿易関係者・IT企業・行政機関など、様々な関係者が情報共有し、協力して貿易手続のDXを進めるための場や機会を提供することを目指す」という目的は、OIの観点からも、大変有意義なものと期待しております。
より具体的に、TRGのミッションを産官学それぞれの関係者の観点から整理すれば、次のようになるでしょう。所管官庁は、TRGを経由して貿易DXに係る施策を周知し、補助金などの利用促進を図ることとなります。実務家(貿易プラットフォーム、荷主、物流、銀行、保険などの関連業界)は、それぞれの提供する貿易DX関連プロダクトやサービスについて情報発信を行います。研究者(大学、業界団体などの研究機関)は、研究成果の他、研究途上もしくは構想段階から、世に問うこととなります。
他方、単にTRG/tradigi.jp経由で産官学それぞれの関係者が一方向で情報発信する以上に重要なのは、産官学相互の情報連携強化であることは言うまでもないでしょう。例えば、所管官庁の施策に対する実務家、研究者による意見・提案の情報発信を行うことで、官側の政策立案に役立てることや、研究者の行う、産官に対するヒアリング先の紹介や、共同研究のマッチングなど、中長期的に取り組むべき役割だと考えております。「◯×□」といった従来の形にとらわれない自由な組み合わせで、新しい試みを繰り返す場を提供することこそが、貿易DXに資すると考えます。
いずれにせよ、これらの目的を実現する為には、一人でも多くの関係者が、TRG/tradigi.jpに興味を持って頂き、積極的に参加して頂くことが必須です。TRGとして、皆様に参加して頂くための魅力ある仕組み作りに取組む所存でございますが、皆様のご支援、ご協力も必用不可欠です。どうか宜しくご支援の程、お願い申し上げます。
花木正孝 先生 プロフィール
- 近畿大学 大学院 商学研究科/経営学部 商学科 教授
- 1989年大阪大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。外為取引先を中心に法人営業を担当後2003年より大阪外為センター(現グローバルサービス部)勤務。2015年より近畿大学経営学部商学科准教授、2021年より教授。2022年博士(商学)、2025年4月より現職。日本貿易学会理事、日本港湾経済学会理事、経済産業省WG委員。2025年、日本港湾経済学会 学会賞、日本貿易学会 学会賞を受賞。
- 現在の研究課題は「貿易取引の電子化、FinTech活用等、資金決済方法/ファイナンス手法の高度化」「貿易取引における為替リスクや売掛債権回収リスクのヘッジ手法の高度化」「マネー・ローンダリング防止等、外国為替コンプライアンス上の課題」等。株式会社NTTデータとの共同研究として「マネロン防止・経済安全保障対策への貿易デジタルデータ活用についての調査・研究」 4を実施中。
【脚注】
- 2024 年12 月出版の『FinTech 時代の貿易代金決済電子化-失敗事例からの教訓と示唆』(株)文眞堂 に対して、2 学会より学会賞を授与された。① 日本港湾経済学会 第33 回学会賞(北見俊郎賞)著書の部、② 2025 年度 日本貿易学会 学会賞 著書の部(単著)
- 経済産業省(2024)『デジタルガバナンス・コード3.0~DX 経営による企業価値向上に向けて~』2 頁
- Henry William Chesbrough (2003) “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, Harvard Business Review Press
- 4 近畿大学プレスリリース① 近畿大学とNTT データ、マネロン防止・経済安全保障対策への貿易デジタルデータ活用について共同研究をスタート ~産官学連携の取り組み推進により、新たな業界共通プラットフォームの構築を目指す~ 2024-11-22 https://newscast.jp/news/3408308、② 貿易デジタルデータ活用により、マネロン防止・経済安全保障対策の強化および業務効率化への有効性を確認 ~貿易書類のチェック作業効率化により、約20%の工数削減~ 2025-05-16 https://newscast.jp/news/6126993